これはずいぶん前からチェックしていて、我慢できず……私にとって過去一番充実するモンドリアンとその作品たちでした。
日本での展覧会は23年ぶりだとか! さていったい何が待ち受けていたのでしょうか。
それではご紹介していきます!
企画展情報
名称:モンドリアン展
会場:豊田市美術館
会期:2021年7月10日〜9月20日
休日昼間に訪館。豊田市美術館は2年前のクリムト展ぶりでした。
クリムト展も本当によかった……当時の訪問記事があるので、気になる方は是非チェックしてください。
展示作品について
感性だけじゃない作風
モンドリアンといえば、キャンバスに走らせた縦横無尽な線。幾何学的な表現を追求し、新造形主義をはじめたお方です。
「コンポジション」シリーズで検索すれば、一度は見たことがあるかもしれません。
今まで、背景の白い・直線の黒・線で四角どった赤、黄、青……の5色だけ(実際は灰色の四角があって、実物を見るまで分かりませんでした! 訪問あるある!)のものだと勘違いしていました。色やパターンにもっとずっとバリエーションがあって、試行してきた様子が感じられます。
そのうちの一つに、色使いが重要なようでした。モンドリアンは色使いに三原色や補色(赤と緑、黄と紫のような正反対の色の組み合わせ)を用いています。明暗・清濁も影響しますが、両極性な特徴を持つ補色や原色って並べてみるとかなりギラギラして見える心理効果があります。暗い青とオレンジで描いた「オランダカイウ(カラー);青い花」が分かりやすかったですね。
モンドリアンはこれを利用して、描くものをより図形的に捉えようとしたのかなぁと。
アートを一括りにはできなくて、特にこれといったモチーフを使わない抽象絵画は見た者によって受け取り方が異なってきます。この新造形主義(位置的には抽象絵画です)のロジカルな要素とでも言いましょうか……私はそれが面白くてとても飲み込みやすかったです。
そうそう、後日調べてみたのですが、新造形主義はミニマル・アート(ミニマリズム)へ継承されているそうです。関心がある方はぜひモンドリアンをチェックしてみてください。彼の試みてきたことや作品の意図に、何か感じるところがあるかもしれません。
描き手の視点
モンドリアンは絵を描き始めた時から、独特のフィルターでも持っていたように図形的やらパターンやら要素を持つモチーフを絵におさめています。「ヘイン河畔 水辺の木々」という作品は、河とその向こう岸の木々が描かれています。下半分を占める河には水面に映る木々。それはシンメトリーに近い構図です。へイン河畔は別の構図で他にも絵が残されていますが、彼のフィルターを通して図形的、シンメトリーが表現されていました。
私の解釈で説明するのなら、シンメトリーや四角形などの対称的な特徴があるものへの関心をずっと作品に昇華していたようでした。
何かスケッチをする時、好きな構図や直感的に良いと思った風景を選ぶケースがありますよね。その構図を選んだ理由はきっと人それぞれです。モンドリアンが選ぶ時は、幾何学的な要素があるから、だったのかもしれません。「雄牛」は背景が見えないくらい画面ギリギリに収まるように牛が描かれていました。それは風景画でも動物画でもなく、牛を横から見た時の体のライン、牛のフォルムに注目している画だったと分かります。
平面を壊せ?
前述した「コンポジション」シリーズですが、その存在から現代に広がるデザインというデザインに影響を及ぼしています。それは絵だけに留まらず、建築や家具へと広がりました。シリーズの内、ジャズから着想を得た作品がありまして、改めて発想と転換の良いサイクル例だと思います。
モンドリアンの「コンポジション」シリーズの線はとても重要な意味があるそうです。ただ単に図形の線というわけではありませんでした。
線を引くことで、平面を破壊しようとしたーー。
ピート・モンドリアン
まあ驚きです。絵画は物理的に平面です。まあ立体にならないこともないのですが……。キャンバス(平面)に向かって「平面を壊そう!」なんて、ね、普通はちょっと思わないですよね。
終わりに
他にもいろいろと紹介したいし、展示を踏まえての自己解釈を述べていきたいのですが。なんだか冗長化してしまう気がしたので別の機会にしたいと思います。それくらい、モンドリアンへの関心が高まりました。
気に入ったアーティストから得られるものって貴重ですよね。皆さんにはどのような関心があって、どのような影響を受けているのでしょうか。私、気になります! なんつて。
それではまた次の記録が残されるまで、またね〜。
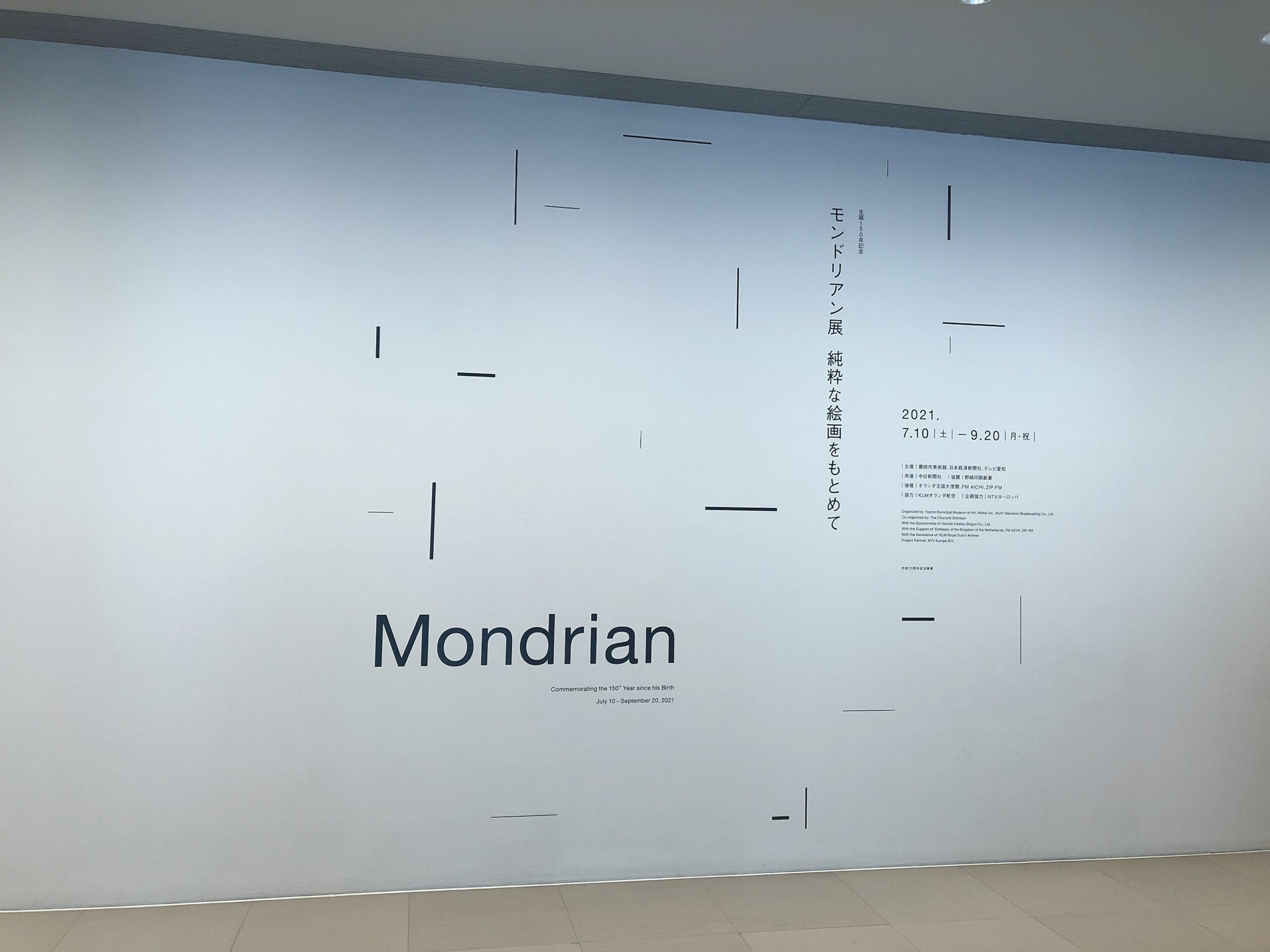
 vol.2「クリムト展 ウィーンと日本 1900」
vol.2「クリムト展 ウィーンと日本 1900」 

コメント